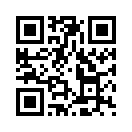2013年03月19日
「「する」ではなく「いる」」と「なる」 上野圭一・辻信一「スローメディスン」の示唆
最近、上野圭一・辻信一「スローメディスン」(大月書店2009年)という本を読んだ。共感できるところが多い本だ。
この本には、「「する」ではなく「いる」」という一節がある。そこには、次のようなことが書かれている。
「ぼくたちは今、「する」ことに取り憑かれた時代に生きているのではないでしょうか。「する」ことに取り憑かれているとはどういうことか。人間の価値を、いかにうまく「する」かで決めるということです。現代社会のキーワードである競争や効率や生産性も、いかによりよく「する」か、より早く「する」か、にかかっています。なぜより早く「する」ことが重要かといえば、より多く「する」必要があり、より多くの結果を出さなければならないから。」P127-8
「人間の存在はやっぱり「いる」なんです。ぼくらは動物ですし、「する」ことは一種の宿命のようなもので、いつも何かしていなかったら生きていけない存在なわけです。さらにいえば、この「いる」と「する」は人間の本質的な両面で、要は、その間にどうバランスをとるか、なんだと思います。さっきも言ったように、病や老いとは「することができなくなること」だと定義できる。病が癒えると、また「することができる」状態にもどっていくのですが、老いは不可逆的にだんだんできなくなっていって、「する」が減っていって、最後に死を迎える。死とはまったく「する」ことができない、いわば「する」ゼロ状態のことですよね。「する」に取り憑かれた社会、「する」ことだけで人の価値を決める社会――ぼくは「するする社会」と呼んでいるんですが――では、「病なんてさっさと治して、またできる(する)ようになれ」ということを要求されますし、老いに対しても、「え、そんなことさえできないの?」というぐあいに、否定的にとらえるしかない。そして死も完全に無能な状態として否定的にとらえれば、無価値、無意味ですよね。」P128-9
「どうして「する」に取り憑かれる人ばかり出てくるのでしょうね。それがぼくにはわからない。その仕組みから降りることは、誰にでもできると思うんです。事実、やってきた人もたくさんいます。ぼくも降りてきた。」P130
「健全であり健常であり健康であるということがかえって、ぼくたちを逆に「する」ことに取り憑かれやすく、システムにとりこまれやすくしているのかもしれない。若いときは、寝る時間も惜しんでバリバリ働いたりして、いくらでも、何でもできるような気になっている人が多いじゃないですか。子どもに対しても、「強くあれ」、「がんばれ」「なんにでも挑戦しろ」、「あきらめずにやりつづけろ」というふうにずっと駆り立てていく。でも病気になると、「ちょっと待てよ」とふと我に返るわけです。病気のときは「する」ことが制限されて、「いる」しかなくなる。「人間は何のために生きているんだっけ」と思わされる瞬間です。あるいは、自分の子どもがかなり重い病気や怪我になったとき、「この子が生きてさえいてくれれば、他は何も望まない」と思えたりする。」P131
私は、こうした主張におおいに共感する。「する」は確かに必要ではあるが、現在は、「する」過剰であり、「する」が「いる」を過剰支配しているように思われる。働き過ぎ、ワーカーホリックはそのあらわれだろう。その結果、「いる」の価値が過剰に低められているのではなかろうか。
ところで、「する」には、目標や計画を立てて、目標実現に向けて作業過程を綿密に管理して展開するものが多いが、それだけではない。そうした目標や計画なしに「する」ものが結構ありはしないだろうか。流れの中で、いろいろなモノ・コト・ヒトに出会いながら、その場の状況のなかで「する」ものが色々とある。その際には、思いもしなかった出会い発見創造があるだろう。そうしたものが蓄積していく中で、「なる」と言う形で、なにかが生まれる、できてしまう、という事が結構ある。
計画的な「する」ばかりしていると、想定外にでてきた「なる」モノ・コト・ヒトの豊かさを見失う事があるだろう。その意味で、「なる」「なってしまう」というものも大切にしたい。
 写真は本文に関係なく、我が家とタマグスクを、南側から見る。遠くからでも、我が家のブーゲンビリアが目立つようになった。山の一番高いところがタマグスク。
写真は本文に関係なく、我が家とタマグスクを、南側から見る。遠くからでも、我が家のブーゲンビリアが目立つようになった。山の一番高いところがタマグスク。
この本には、「「する」ではなく「いる」」という一節がある。そこには、次のようなことが書かれている。
「ぼくたちは今、「する」ことに取り憑かれた時代に生きているのではないでしょうか。「する」ことに取り憑かれているとはどういうことか。人間の価値を、いかにうまく「する」かで決めるということです。現代社会のキーワードである競争や効率や生産性も、いかによりよく「する」か、より早く「する」か、にかかっています。なぜより早く「する」ことが重要かといえば、より多く「する」必要があり、より多くの結果を出さなければならないから。」P127-8
「人間の存在はやっぱり「いる」なんです。ぼくらは動物ですし、「する」ことは一種の宿命のようなもので、いつも何かしていなかったら生きていけない存在なわけです。さらにいえば、この「いる」と「する」は人間の本質的な両面で、要は、その間にどうバランスをとるか、なんだと思います。さっきも言ったように、病や老いとは「することができなくなること」だと定義できる。病が癒えると、また「することができる」状態にもどっていくのですが、老いは不可逆的にだんだんできなくなっていって、「する」が減っていって、最後に死を迎える。死とはまったく「する」ことができない、いわば「する」ゼロ状態のことですよね。「する」に取り憑かれた社会、「する」ことだけで人の価値を決める社会――ぼくは「するする社会」と呼んでいるんですが――では、「病なんてさっさと治して、またできる(する)ようになれ」ということを要求されますし、老いに対しても、「え、そんなことさえできないの?」というぐあいに、否定的にとらえるしかない。そして死も完全に無能な状態として否定的にとらえれば、無価値、無意味ですよね。」P128-9
「どうして「する」に取り憑かれる人ばかり出てくるのでしょうね。それがぼくにはわからない。その仕組みから降りることは、誰にでもできると思うんです。事実、やってきた人もたくさんいます。ぼくも降りてきた。」P130
「健全であり健常であり健康であるということがかえって、ぼくたちを逆に「する」ことに取り憑かれやすく、システムにとりこまれやすくしているのかもしれない。若いときは、寝る時間も惜しんでバリバリ働いたりして、いくらでも、何でもできるような気になっている人が多いじゃないですか。子どもに対しても、「強くあれ」、「がんばれ」「なんにでも挑戦しろ」、「あきらめずにやりつづけろ」というふうにずっと駆り立てていく。でも病気になると、「ちょっと待てよ」とふと我に返るわけです。病気のときは「する」ことが制限されて、「いる」しかなくなる。「人間は何のために生きているんだっけ」と思わされる瞬間です。あるいは、自分の子どもがかなり重い病気や怪我になったとき、「この子が生きてさえいてくれれば、他は何も望まない」と思えたりする。」P131
私は、こうした主張におおいに共感する。「する」は確かに必要ではあるが、現在は、「する」過剰であり、「する」が「いる」を過剰支配しているように思われる。働き過ぎ、ワーカーホリックはそのあらわれだろう。その結果、「いる」の価値が過剰に低められているのではなかろうか。
ところで、「する」には、目標や計画を立てて、目標実現に向けて作業過程を綿密に管理して展開するものが多いが、それだけではない。そうした目標や計画なしに「する」ものが結構ありはしないだろうか。流れの中で、いろいろなモノ・コト・ヒトに出会いながら、その場の状況のなかで「する」ものが色々とある。その際には、思いもしなかった出会い発見創造があるだろう。そうしたものが蓄積していく中で、「なる」と言う形で、なにかが生まれる、できてしまう、という事が結構ある。
計画的な「する」ばかりしていると、想定外にでてきた「なる」モノ・コト・ヒトの豊かさを見失う事があるだろう。その意味で、「なる」「なってしまう」というものも大切にしたい。
 写真は本文に関係なく、我が家とタマグスクを、南側から見る。遠くからでも、我が家のブーゲンビリアが目立つようになった。山の一番高いところがタマグスク。
写真は本文に関係なく、我が家とタマグスクを、南側から見る。遠くからでも、我が家のブーゲンビリアが目立つようになった。山の一番高いところがタマグスク。Posted by 浅野誠 at 06:24│Comments(0)
│生き方・人生