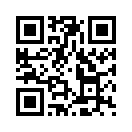2012年06月14日
明 倭寇 琉球 グスク時代 吉成本5
これまでも、グスク時代の沖縄と倭寇との関連が指摘されてきたが、本書は、そのことを重視し、端的に次のように主張する。
「(明による)琉球への優遇策が倭寇対策であることは、倭寇活動の活発化、琉球への優遇策、倭寇活動の減少(十五世紀半ば頃)、琉球への優遇策の廃止という一連の流れを考えれば一目瞭然である。」P251
このことをより詳しく、村井章介論を紹介していく。
「交易の舞台に琉球をおしだしたのが明の海禁政策――明が中国人民を海上の反権力集団(特に倭寇)から切りはなそうとして、その下海および海外渡航を禁止した――であり、その結果、中国商人はシナ海上の交易から撤退を余儀なくされ、地の利を生かしてこの空隙を埋めたのが琉球であった。そして、明側からみれば、海禁により自国商人からの入手が不可能になった海外産品を入手するために、琉球という国家を自己の体制のもとに編入した。比喩的に言えば、琉球は明の貿易商社になったのである。その根拠として、以下の四つがある。①明の福建地方から渡来した人びとが那覇の一角に久米村と呼ぶ居留地をつくり、日本以外の諸外国との外交を専掌した。『歴代宝案』はかれらのもとに伝えられる。②明初に琉球が対外交易に用いた船は、すべて明皇帝から賜与されたものであったことが『歴代宝案』第一集から知られる。③琉球の国家中枢にあって貿易に深く関与した王相・長史・典簿などの官職は、明の王相府または王府の制に拠るもので、当初は直接明から任命されていた。④明は福州に琉球専門の市舶司と公館(柔遠駅)を設けて、その使節を優遇した。しかし、これは裏を返して言えば、琉球の貿易実務上の担い手が中国人だったことを意味しており、海禁政策によって行き場を失った中国商人は、琉球の国営貿易の請負に合法的な活動の場を見いだした。それは琉球が交易を行う東南アジア諸国でも事情は同じであり、海禁政策のもとで中国商人が合法性を獲得するための一形式であった」P215~6
「明に侵攻、密輸していた倭寇を琉球に引き受けさせることによって、一三八三年(洪武十六)以降、琉球の朝貢回数が急激に増えたということになる。琉球を舞台に、倭寇の非合法的な活動を、朝貢という形式に転化させたということである。」P218
鉄についての察度の「常識」的話も、次のように書く。
「察度は鉄を買い入れ、農具をつくって農民に配ったとされる。しかし、『朝鮮王朝実録』(一四七九年)の、与那国島に漂着し、沖縄島まで見聞した金非衣らの話では、与那国で「鉄冶有り。而ども耒耝を造らず」とあるように、鉄製の耕起具(スキ、クワ)が存在する事実を窺うことはできない。安里進は、こうした状況について、鉄が欠乏していたというよりは、耕地拡大に向かわなかったためであり、鉄は農具よりも武器に大量投入されたとする(中略)。確かに、先の『朝鮮王朝実録』の漂着記事では、沖縄島では刀剣、甲冑などが存在することが述べられている。」P238 ※耒耝とは農具の「すき」のこと
「第一尚氏の時代である十五世紀の半ばまで倭寇は活動するが、その活動が衰退していくとともに琉球に対する朝貢の優遇策が廃止されることも、倭寇の「受け皿」としての「三山時代」から倭寇的な性格を依然としてとどめる第一尚氏時代の沖縄島の勢力のあり方を示すものと言ってよい。」P252
これまでのグスク時代にかかわる有力説とはかなり異なる、これらの紹介・提起は、私にとっては大変刺激的である。これらが新たな有力説とされるなら、たとえば、次のような問いが生まれてくる。
当時の沖縄の産業別人口構成はどうなっていたのか。端的にいって、交易従事者と農業従事者との比率だ。そして、各々の従事者がどのような人々だったのか。
交易をになう組織・共同体はどのようなものだったのか。これまでは農業共同体としてイメージされていたシマ共同体は、交易とはどのような関係にあったのか。
信仰・神はどうなっていたのか。特に、農業と交易との関わりのなかで。
複数の文化が接触・交流・協同することが、何をもたらしたのか。
交易がこれだけ重要な位置にあったとするなら、複数の言語使用が求められるが、その実態はどうだったのか。そこに教育問題が浮上するが、それはどうだったのか。
このように、新たな問いかけがいくつも生まれてくる。
写真は本文にかかわりなく、我が家玄関脇のキバナタイワンレンギョウ。花も実も写っている。

「(明による)琉球への優遇策が倭寇対策であることは、倭寇活動の活発化、琉球への優遇策、倭寇活動の減少(十五世紀半ば頃)、琉球への優遇策の廃止という一連の流れを考えれば一目瞭然である。」P251
このことをより詳しく、村井章介論を紹介していく。
「交易の舞台に琉球をおしだしたのが明の海禁政策――明が中国人民を海上の反権力集団(特に倭寇)から切りはなそうとして、その下海および海外渡航を禁止した――であり、その結果、中国商人はシナ海上の交易から撤退を余儀なくされ、地の利を生かしてこの空隙を埋めたのが琉球であった。そして、明側からみれば、海禁により自国商人からの入手が不可能になった海外産品を入手するために、琉球という国家を自己の体制のもとに編入した。比喩的に言えば、琉球は明の貿易商社になったのである。その根拠として、以下の四つがある。①明の福建地方から渡来した人びとが那覇の一角に久米村と呼ぶ居留地をつくり、日本以外の諸外国との外交を専掌した。『歴代宝案』はかれらのもとに伝えられる。②明初に琉球が対外交易に用いた船は、すべて明皇帝から賜与されたものであったことが『歴代宝案』第一集から知られる。③琉球の国家中枢にあって貿易に深く関与した王相・長史・典簿などの官職は、明の王相府または王府の制に拠るもので、当初は直接明から任命されていた。④明は福州に琉球専門の市舶司と公館(柔遠駅)を設けて、その使節を優遇した。しかし、これは裏を返して言えば、琉球の貿易実務上の担い手が中国人だったことを意味しており、海禁政策によって行き場を失った中国商人は、琉球の国営貿易の請負に合法的な活動の場を見いだした。それは琉球が交易を行う東南アジア諸国でも事情は同じであり、海禁政策のもとで中国商人が合法性を獲得するための一形式であった」P215~6
「明に侵攻、密輸していた倭寇を琉球に引き受けさせることによって、一三八三年(洪武十六)以降、琉球の朝貢回数が急激に増えたということになる。琉球を舞台に、倭寇の非合法的な活動を、朝貢という形式に転化させたということである。」P218
鉄についての察度の「常識」的話も、次のように書く。
「察度は鉄を買い入れ、農具をつくって農民に配ったとされる。しかし、『朝鮮王朝実録』(一四七九年)の、与那国島に漂着し、沖縄島まで見聞した金非衣らの話では、与那国で「鉄冶有り。而ども耒耝を造らず」とあるように、鉄製の耕起具(スキ、クワ)が存在する事実を窺うことはできない。安里進は、こうした状況について、鉄が欠乏していたというよりは、耕地拡大に向かわなかったためであり、鉄は農具よりも武器に大量投入されたとする(中略)。確かに、先の『朝鮮王朝実録』の漂着記事では、沖縄島では刀剣、甲冑などが存在することが述べられている。」P238 ※耒耝とは農具の「すき」のこと
「第一尚氏の時代である十五世紀の半ばまで倭寇は活動するが、その活動が衰退していくとともに琉球に対する朝貢の優遇策が廃止されることも、倭寇の「受け皿」としての「三山時代」から倭寇的な性格を依然としてとどめる第一尚氏時代の沖縄島の勢力のあり方を示すものと言ってよい。」P252
これまでのグスク時代にかかわる有力説とはかなり異なる、これらの紹介・提起は、私にとっては大変刺激的である。これらが新たな有力説とされるなら、たとえば、次のような問いが生まれてくる。
当時の沖縄の産業別人口構成はどうなっていたのか。端的にいって、交易従事者と農業従事者との比率だ。そして、各々の従事者がどのような人々だったのか。
交易をになう組織・共同体はどのようなものだったのか。これまでは農業共同体としてイメージされていたシマ共同体は、交易とはどのような関係にあったのか。
信仰・神はどうなっていたのか。特に、農業と交易との関わりのなかで。
複数の文化が接触・交流・協同することが、何をもたらしたのか。
交易がこれだけ重要な位置にあったとするなら、複数の言語使用が求められるが、その実態はどうだったのか。そこに教育問題が浮上するが、それはどうだったのか。
このように、新たな問いかけがいくつも生まれてくる。
写真は本文にかかわりなく、我が家玄関脇のキバナタイワンレンギョウ。花も実も写っている。

Posted by 浅野誠 at 06:02│Comments(0)
│沖縄の歴史・民俗