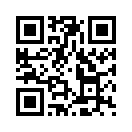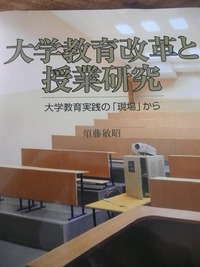2012年11月30日
授業開始終了時間 教師の位置・目線 大学授業の小ワザ3
私は、授業開始10分前ほどに教室に入るのが平均だ。9年前までの中京大学時代では、5分ぐらい前には教室に入っていた。教室に行く前には、授業進行メモを再確認しながら、授業進行のイメージトレーニングをし、模造紙・付箋紙・マジックといった必要用具を持つ。といっても、これらにかける時間は5分ほどだが。
現在の琉球大学授業では、教室の鍵を私が開けるので、20分ほど前に行くことが多い。グループで準備作業する受講生たちがいるからだ。昼休み後の3限なので、それができる。
教室では、用具配置をし、今日の進行などの情報を板書する。
そして、教室に来ている学生たちとおしゃべりをする。授業に関係することしないこといろいろ。
10人ぐらい学生が集まると、机・椅子の配置換えを指示する。学生が要領を呑み込めない時は、私が配置換えを始めて、イメージを示す。机を下げ椅子だけを円形に並べ、中央広場を作るなどだ。
科目によっては、事前ミニメモを受講生が持ってくるので、捺印またはサインをする。
事前ミニメモについて少し説明しよう。 ミニメモのことは、これまでにも書いたが、そのミニメモの浅野確認欄を毎回二カ所、スタート欄とエンド欄を作り、そのスタート欄を「事前ミニメモ」と名付けた。
二つの効果がある。一つは、受講生が時間通りに来る。もう一つは、事前予習というほど大げさではなくても、1~2行の記入で、授業開始前に授業での取り組み準備をしてもらうというのだ。
スタート欄をつくったきっかけは、ある授業で、20分後ぐらいにくる課長出勤どころか、40分後の部長出勤、60分後の社長出勤、80分後の会長出勤という豪傑たちがいたので、時間通りに来ると、ポイントが一つ加えるシステムを作ったことにある。ということで、私の授業では時間通りくるのが定番になった。
授業終了は、多くの場合、10~15分前ぐらいに全体進行を終える。そして、事後ミニメモを記入提出してもらう。その後、机椅子などの後片付けがある。グループ討論がずれこむグループがあり、ミニメモ記入提出が少し遅れるグループがあるが、受講生たちが、終了時刻には退室できるようにしている。
次は、授業中、私が教室のなかのどこにいるか、という教師の位置の話だ。
授業開始直後、今日の授業の進行説明、課題提起・活動提起といったことを5~15分間することが多いが、その時は、黒板前にいる時もあるが、そんなに多くない。全体を丸くして座ったり、グループ単位に座ったりするので、それらの「あちこち」に、立って、あるいは座って話すことが多い。
作業・討論がすすむと、「あちこち」に出かけるのが普通だ。授業中の歩数をはかったことはないが、かなりありそうだ。
説明や歩く時は立っているが、たいていは学生の近くに座って、作業や討論に口をはさむことが多い。だから、上から学生たちを見るというのではなく、学生と同じ高さ・目線で付き合うことが多い。
教室の前面や中央からはずれたところに位置する学生・グループがあると、その近くに行くことがとても多い。その近くから全体にむかって発言することもある。
学生が全体に向かって発言する際、声が小さいことが多い。70人ぐらいになると、普通に話しても聞きにくい学生が多くなる。そこで、最近の私の口癖「老人性難聴なんで、大きな声が言ってくれませんか」と頼む。あるいは、「老人性難聴なんで」といって、その学生のところまで歩いていこうとする。すると、学生は大きな声を出し始める。
ただ「大きな声を出して下さい」とだけ言うより、効果絶大だ。私の「聞こえ」は、年齢相応の「老人性難聴」で、補聴器を必要とするほどではないが。
教職科目を担当する時、かつては、「教師の仕事は、子どもに声が通る必要があるから、そういう声を出してください」と頼んだこともあった。
写真は本文と関係なく、ガザニア

現在の琉球大学授業では、教室の鍵を私が開けるので、20分ほど前に行くことが多い。グループで準備作業する受講生たちがいるからだ。昼休み後の3限なので、それができる。
教室では、用具配置をし、今日の進行などの情報を板書する。
そして、教室に来ている学生たちとおしゃべりをする。授業に関係することしないこといろいろ。
10人ぐらい学生が集まると、机・椅子の配置換えを指示する。学生が要領を呑み込めない時は、私が配置換えを始めて、イメージを示す。机を下げ椅子だけを円形に並べ、中央広場を作るなどだ。
科目によっては、事前ミニメモを受講生が持ってくるので、捺印またはサインをする。
事前ミニメモについて少し説明しよう。 ミニメモのことは、これまでにも書いたが、そのミニメモの浅野確認欄を毎回二カ所、スタート欄とエンド欄を作り、そのスタート欄を「事前ミニメモ」と名付けた。
二つの効果がある。一つは、受講生が時間通りに来る。もう一つは、事前予習というほど大げさではなくても、1~2行の記入で、授業開始前に授業での取り組み準備をしてもらうというのだ。
スタート欄をつくったきっかけは、ある授業で、20分後ぐらいにくる課長出勤どころか、40分後の部長出勤、60分後の社長出勤、80分後の会長出勤という豪傑たちがいたので、時間通りに来ると、ポイントが一つ加えるシステムを作ったことにある。ということで、私の授業では時間通りくるのが定番になった。
授業終了は、多くの場合、10~15分前ぐらいに全体進行を終える。そして、事後ミニメモを記入提出してもらう。その後、机椅子などの後片付けがある。グループ討論がずれこむグループがあり、ミニメモ記入提出が少し遅れるグループがあるが、受講生たちが、終了時刻には退室できるようにしている。
次は、授業中、私が教室のなかのどこにいるか、という教師の位置の話だ。
授業開始直後、今日の授業の進行説明、課題提起・活動提起といったことを5~15分間することが多いが、その時は、黒板前にいる時もあるが、そんなに多くない。全体を丸くして座ったり、グループ単位に座ったりするので、それらの「あちこち」に、立って、あるいは座って話すことが多い。
作業・討論がすすむと、「あちこち」に出かけるのが普通だ。授業中の歩数をはかったことはないが、かなりありそうだ。
説明や歩く時は立っているが、たいていは学生の近くに座って、作業や討論に口をはさむことが多い。だから、上から学生たちを見るというのではなく、学生と同じ高さ・目線で付き合うことが多い。
教室の前面や中央からはずれたところに位置する学生・グループがあると、その近くに行くことがとても多い。その近くから全体にむかって発言することもある。
学生が全体に向かって発言する際、声が小さいことが多い。70人ぐらいになると、普通に話しても聞きにくい学生が多くなる。そこで、最近の私の口癖「老人性難聴なんで、大きな声が言ってくれませんか」と頼む。あるいは、「老人性難聴なんで」といって、その学生のところまで歩いていこうとする。すると、学生は大きな声を出し始める。
ただ「大きな声を出して下さい」とだけ言うより、効果絶大だ。私の「聞こえ」は、年齢相応の「老人性難聴」で、補聴器を必要とするほどではないが。
教職科目を担当する時、かつては、「教師の仕事は、子どもに声が通る必要があるから、そういう声を出してください」と頼んだこともあった。
写真は本文と関係なく、ガザニア

Posted by 浅野誠 at 06:57│Comments(0)
│大学