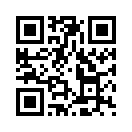2013年03月11日
「浅野誠沖縄論シリーズ1 沖縄」のホームページ掲載
私は、1972年4月に沖縄に住み始めて以降、年々沖縄に「はまってきた」。途中14年ほど愛知県に住むが、結局は沖縄に戻ってきた。今や、現住所だけでなく本籍地も沖縄県にして9年近くなり、通算すると、沖縄とのかかわりは41年、在住期間は、26年になる。
その間、沖縄についていろいろと考え、いろいろと書いてきた。代表的には、「沖縄教育の反省と提案」(1983年明治図書)、「沖縄県の教育史」(1991年思文閣)、「沖縄おこし・人生おこしの教育」(2011年アクアコーラル企画)などの教育関連書だ。とはいえ、教育以外のことにも強い関心をもってきた。現在も、地域おこし沖縄おこしに直接かかわっている。
だから、開設した旧ホームページ(2003~2007年)にも、ブログ(2007年~)にも、沖縄にかかわってたくさんのことを書いてきた。それらの記事は、ブログの容量を越すために、3年もたたないうちに消去している。
そこで、今回、2003~2010年執筆のものを以下に示す4つのカテゴリー別に編集して、そのシリーズ第一集を、新ホームページ(浅野誠・浅野恵美子の世界http://asaoki.jimdo.com)に掲載した。
1.沖縄 (今回)
2・沖縄の暮らし(次回予定)
3.沖縄の歴史 (夏予定)
4.沖縄の教育 (夏予定)
その「1.沖縄」に収録した記事一覧を示しておこう。
11.沖縄とは?
沖縄印象
沖縄にいることは引っ込むことだという感覚
沖縄についてのステロタイプ的認識
ステロタイプ思考「沖縄は遅れている」が見落としていること
琉球大学編『やわらかい南の学と思想』(沖縄タイムス社2008年)
「うちなーぐち」は沖縄語――宮良信詳説 琉球大学本2
国連人権委員会『沖縄先住民の権利保護を』という新聞記事
国連人権委員会『沖縄先住民』問題勧告の英文見つける
『沖縄先住民』問題、続論 この勧告の重大性
そっけない政府答弁書 沖縄/琉球先住民(族)問題
薩摩の琉球入り400年の2009年の企画
多田治『沖縄イメージを旅する』(中公新書2008年)を読む1
多田本2 本土からのツーリストのまなざしとナショナリズム
多田本3 貧困イメージと「古きよき琉球へのロマン主義」
多田本4 「愛郷心を通して愛国心を示す」
多田本5 「蔓延する沖縄病」と「癒し」
多田本6 イメージ消費 脱線話―観光でないツーリストたち
多田本7 沖縄の「内と外」 「沖縄ブームから沖縄スタイルへ」
多田本8 沖縄イメージ ちゅらさん モンパチ 琉球
多田本9 観光はいったん否定されることを通して受け入れられる
どんな沖縄イメージを発信するのか
「沖縄の出生率はなぜ高いのか?」
魚 昆布 鰹節 じゃこ
大国と沖縄
民族自決と精神 沖縄
自ら全国に「同化」していこうとする発想
外来物をチャンプルー化し、沖縄独自のものを作り出していくこと
自然・神・心・戦 千葉大学学生の礼状に見る沖縄印象
Momotoモモト・・・新刊雑誌
12.移民移住・多文化・バイリンガル
移住・交流の視点から沖縄をとらえると
多文化のなかで生きる 安藤由美・鈴木規之・野入直美編『沖縄社会と日系人・外国人・アメラジアン』(クバプロ2007年)を読む
英日西仏語雑誌OKINAWA 小川京子さんのクバ物語掲載
沖縄と移民
村上呂里さんの沖縄の言語教育にかかわる鋭く示唆的な論文を読む
沖縄とバイリンガル 村上さんの本から学ぶ
この本の私にとっての主ポイント 村上さんの本から学ぶ2
日本語創造とウチナーグチ 個人体験 村上さんの本から学ぶ3
「沖縄的なもの」への肯定と否定 村上さんの本から学ぶ4
言語観 生活・文化と道具・科学 村上さんの本から学ぶ5
沖縄的なものを教える 文化と生活現実 村上さんの本から学ぶ6
バイリンガル再論 村上さんの本から学ぶ7
地域・国・グローバルという視野で 村上さんの本から学ぶ8
実践をどう展開していくか 村上さんの本から学ぶ9
13.政治
沖縄国際大学米軍ヘリ墜落
ステルス戦闘機F22Aが上空を轟音で飛ぶ
飛行機事故
『教科書検定』県民集会
県民集会に参加した人々と交通手段
県の旅券センター 久しぶりの国際通
会場外会場?も人がいっぱい 基地撤去集会 会場溢れる
沖縄自治の創造へ 『沖縄「自立」への道を求めて』を読む1
基地認識をリアルに 『沖縄「自立」への道を求めて』を読む3
14.沖縄の産業・沖縄おこし
子ども未来ゾーンのすごい構想
沖縄道路事情と沖縄経済
出稼ぎ
沖縄の開業率・廃業率日本一は喜ぶべきか悲しむべきか
サステイナブル・ツーリスムとニューツリズム 琉球大学本4
新城明久『沖縄の自立に向けて 農業・産業活性化へのヒント』
新城『ヒント本』「沖縄の農業の可能性」壮大で確実な提案
新城『ヒント本』3 教育・平和と結びつけて
新城『ヒント本』4 農林業と観光とを結びつける
私達もお世話になった医介輔 歴史の幕を閉じる
照屋善義『沖縄の陶器 技術と科学』
吉本哲郎『地元学をはじめよう』 ワークショップ型地域づくり
吉本『地元学』本2 発見創造型ワークショップそのもの
吉本『地元学』本3 若者・子どもを「地元」で育てる
「地域に開かれた大学」を越えて、「地域からつくる大学」へ
「南城物語」「南城学」という科目の授業があったらどうでしょう
大江正章「地域の力―食・農・まちづくり」(岩波新書)を読む
「地域の力」本2 I・Uターン 商店街 販売に主導権をもつ農
地域おこしの担い手 字・自治会 自治体職員 議員 フリー
「観光と有機農業の里・阿智」の村づくりの本を読む
阿智本 地域づくり主体 地域自治組織=自治会
阿智本3 村づくり委員会
阿智本4 議員・職員
阿智本5 一人ひとりの人生の質を高められる 全村博物館構想
井口貢編著『入門文化政策 地域の文化を作るという事』
築山崇、桂明宏編著「ふつうの村が動く時」を読む
自立経済の創造へ 『沖縄「自立」への道を求めて』を読む2
 写真は本文には関係なく、我が庭のメイフラワーの花
写真は本文には関係なく、我が庭のメイフラワーの花
その間、沖縄についていろいろと考え、いろいろと書いてきた。代表的には、「沖縄教育の反省と提案」(1983年明治図書)、「沖縄県の教育史」(1991年思文閣)、「沖縄おこし・人生おこしの教育」(2011年アクアコーラル企画)などの教育関連書だ。とはいえ、教育以外のことにも強い関心をもってきた。現在も、地域おこし沖縄おこしに直接かかわっている。
だから、開設した旧ホームページ(2003~2007年)にも、ブログ(2007年~)にも、沖縄にかかわってたくさんのことを書いてきた。それらの記事は、ブログの容量を越すために、3年もたたないうちに消去している。
そこで、今回、2003~2010年執筆のものを以下に示す4つのカテゴリー別に編集して、そのシリーズ第一集を、新ホームページ(浅野誠・浅野恵美子の世界http://asaoki.jimdo.com)に掲載した。
1.沖縄 (今回)
2・沖縄の暮らし(次回予定)
3.沖縄の歴史 (夏予定)
4.沖縄の教育 (夏予定)
その「1.沖縄」に収録した記事一覧を示しておこう。
11.沖縄とは?
沖縄印象
沖縄にいることは引っ込むことだという感覚
沖縄についてのステロタイプ的認識
ステロタイプ思考「沖縄は遅れている」が見落としていること
琉球大学編『やわらかい南の学と思想』(沖縄タイムス社2008年)
「うちなーぐち」は沖縄語――宮良信詳説 琉球大学本2
国連人権委員会『沖縄先住民の権利保護を』という新聞記事
国連人権委員会『沖縄先住民』問題勧告の英文見つける
『沖縄先住民』問題、続論 この勧告の重大性
そっけない政府答弁書 沖縄/琉球先住民(族)問題
薩摩の琉球入り400年の2009年の企画
多田治『沖縄イメージを旅する』(中公新書2008年)を読む1
多田本2 本土からのツーリストのまなざしとナショナリズム
多田本3 貧困イメージと「古きよき琉球へのロマン主義」
多田本4 「愛郷心を通して愛国心を示す」
多田本5 「蔓延する沖縄病」と「癒し」
多田本6 イメージ消費 脱線話―観光でないツーリストたち
多田本7 沖縄の「内と外」 「沖縄ブームから沖縄スタイルへ」
多田本8 沖縄イメージ ちゅらさん モンパチ 琉球
多田本9 観光はいったん否定されることを通して受け入れられる
どんな沖縄イメージを発信するのか
「沖縄の出生率はなぜ高いのか?」
魚 昆布 鰹節 じゃこ
大国と沖縄
民族自決と精神 沖縄
自ら全国に「同化」していこうとする発想
外来物をチャンプルー化し、沖縄独自のものを作り出していくこと
自然・神・心・戦 千葉大学学生の礼状に見る沖縄印象
Momotoモモト・・・新刊雑誌
12.移民移住・多文化・バイリンガル
移住・交流の視点から沖縄をとらえると
多文化のなかで生きる 安藤由美・鈴木規之・野入直美編『沖縄社会と日系人・外国人・アメラジアン』(クバプロ2007年)を読む
英日西仏語雑誌OKINAWA 小川京子さんのクバ物語掲載
沖縄と移民
村上呂里さんの沖縄の言語教育にかかわる鋭く示唆的な論文を読む
沖縄とバイリンガル 村上さんの本から学ぶ
この本の私にとっての主ポイント 村上さんの本から学ぶ2
日本語創造とウチナーグチ 個人体験 村上さんの本から学ぶ3
「沖縄的なもの」への肯定と否定 村上さんの本から学ぶ4
言語観 生活・文化と道具・科学 村上さんの本から学ぶ5
沖縄的なものを教える 文化と生活現実 村上さんの本から学ぶ6
バイリンガル再論 村上さんの本から学ぶ7
地域・国・グローバルという視野で 村上さんの本から学ぶ8
実践をどう展開していくか 村上さんの本から学ぶ9
13.政治
沖縄国際大学米軍ヘリ墜落
ステルス戦闘機F22Aが上空を轟音で飛ぶ
飛行機事故
『教科書検定』県民集会
県民集会に参加した人々と交通手段
県の旅券センター 久しぶりの国際通
会場外会場?も人がいっぱい 基地撤去集会 会場溢れる
沖縄自治の創造へ 『沖縄「自立」への道を求めて』を読む1
基地認識をリアルに 『沖縄「自立」への道を求めて』を読む3
14.沖縄の産業・沖縄おこし
子ども未来ゾーンのすごい構想
沖縄道路事情と沖縄経済
出稼ぎ
沖縄の開業率・廃業率日本一は喜ぶべきか悲しむべきか
サステイナブル・ツーリスムとニューツリズム 琉球大学本4
新城明久『沖縄の自立に向けて 農業・産業活性化へのヒント』
新城『ヒント本』「沖縄の農業の可能性」壮大で確実な提案
新城『ヒント本』3 教育・平和と結びつけて
新城『ヒント本』4 農林業と観光とを結びつける
私達もお世話になった医介輔 歴史の幕を閉じる
照屋善義『沖縄の陶器 技術と科学』
吉本哲郎『地元学をはじめよう』 ワークショップ型地域づくり
吉本『地元学』本2 発見創造型ワークショップそのもの
吉本『地元学』本3 若者・子どもを「地元」で育てる
「地域に開かれた大学」を越えて、「地域からつくる大学」へ
「南城物語」「南城学」という科目の授業があったらどうでしょう
大江正章「地域の力―食・農・まちづくり」(岩波新書)を読む
「地域の力」本2 I・Uターン 商店街 販売に主導権をもつ農
地域おこしの担い手 字・自治会 自治体職員 議員 フリー
「観光と有機農業の里・阿智」の村づくりの本を読む
阿智本 地域づくり主体 地域自治組織=自治会
阿智本3 村づくり委員会
阿智本4 議員・職員
阿智本5 一人ひとりの人生の質を高められる 全村博物館構想
井口貢編著『入門文化政策 地域の文化を作るという事』
築山崇、桂明宏編著「ふつうの村が動く時」を読む
自立経済の創造へ 『沖縄「自立」への道を求めて』を読む2
 写真は本文には関係なく、我が庭のメイフラワーの花
写真は本文には関係なく、我が庭のメイフラワーの花