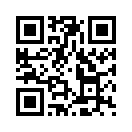2013年02月21日
外側サイクルと内側サイクル シュガーホールと南城おこし2
前回述べた外側サイクルについて、一つ補足しておこう。シュガ―ホールをめぐる評判の高さは、文化ホールや芸術創造をめぐる国の先進的施策で、シュガ―ホールが大型予算を何度も獲得していることにもあらわれている。いってみれば、日本全体のなかでも、先進的な文化ホール創造をしている地方ホールの一つとして、国レベルでも評価されているといえよう。
その外側サイクルのパフォーマンス性の高さは、当然、南城市内の内側サイクルに強い影響をもたらす。無論、内側サイクルも外側サイクルに強い影響をもたらす。
この外側と内側のからみ合いが重要な意味をもつ。たとえば、外側の音楽関係者が、シュガ―ホール内外の演奏で、南城の音楽に強い刺激を与える。逆に、外から来てシュガ―ホール内外の南城の音楽に触れた人が、外で新たな音楽行動に出る。あるいは、その刺激がきっかけとなって、南城のなかに入り込んでくる。
こうしたことを見方を変えていうと、シュガ―ホール内外の南城の音楽・文化は、沖縄全体・日本全体・アジア全体・世界全体の音楽を軸にした文化の渦・サイクルのなかで生きているということだ。
こうした外側サイクルをバックにして、二つ目の内側サイクルを、まずシュガ―ホールでの公演を例にして、考えてみよう。
公演 → 鑑賞体験(感動・リフレッシュ・癒し・エネルギーを得る) → 日常生活の活力・音楽生活の充実 → シュガ―ホール内外での企画への関心 → 公演やワークショップなどの企画参加
観客を例にしたが、このサイクルに演奏者などのサイクルが並行する。
公演 → 公演体験の振り返り → 日常練習 → 次の企画立案 → 公演練習 → 公演
このサイクルは、観客と演奏者の二通りがあるように書いたが、実は、時には演奏者、時には観客というからみがある。また、さらに、今回のシュガ―オーケストラのように、中学生のオーケストラ・ワークショップ参加のようなかかわり方がある。また、新人演奏会で活躍した人が出演者になるという例も多い。さらにまた、「玉露の妖精」のように、南城市民が、オーディションで演奏者になるという流れもある。
こうした流れに、音楽芸能及びそれに関わる多様な文化ジャンルがからんでくるのだが、それらは、音楽を軸にした文化的表現にかかわるものに限定されない。演奏者・観客の精神性・日常生活を豊かにする点にも注目したい。それには娯楽あるいは癒しといったことを含むかもしれない。
そして、日常生活から離陸して高い芸術的なものを感じる場である一方で、日常生活感覚で音楽文化を楽しむという面も結構多い。民謡やジャズのように、生活のなかで楽しむ音楽も結構あるだろうし、高度な芸術的なものと日常的なものとの中間といった感じのものも多い。
シュガ―ホールの特徴は、高度に芸術的なものと見なされがちなものを、観客の感覚にフィットするように、展開する所にもある。今回のシュガ―オーケストラや組踊の公演はそうした色彩が濃厚だ。また、学校や公民館などへの各種の出前企画が、多様な展開をつなぐ橋わたし機能を果たしている点にも注目しておきたい。
(内側サイクルについて、次回に続く)
 写真は、シュガ―ホール
写真は、シュガ―ホール
その外側サイクルのパフォーマンス性の高さは、当然、南城市内の内側サイクルに強い影響をもたらす。無論、内側サイクルも外側サイクルに強い影響をもたらす。
この外側と内側のからみ合いが重要な意味をもつ。たとえば、外側の音楽関係者が、シュガ―ホール内外の演奏で、南城の音楽に強い刺激を与える。逆に、外から来てシュガ―ホール内外の南城の音楽に触れた人が、外で新たな音楽行動に出る。あるいは、その刺激がきっかけとなって、南城のなかに入り込んでくる。
こうしたことを見方を変えていうと、シュガ―ホール内外の南城の音楽・文化は、沖縄全体・日本全体・アジア全体・世界全体の音楽を軸にした文化の渦・サイクルのなかで生きているということだ。
こうした外側サイクルをバックにして、二つ目の内側サイクルを、まずシュガ―ホールでの公演を例にして、考えてみよう。
公演 → 鑑賞体験(感動・リフレッシュ・癒し・エネルギーを得る) → 日常生活の活力・音楽生活の充実 → シュガ―ホール内外での企画への関心 → 公演やワークショップなどの企画参加
観客を例にしたが、このサイクルに演奏者などのサイクルが並行する。
公演 → 公演体験の振り返り → 日常練習 → 次の企画立案 → 公演練習 → 公演
このサイクルは、観客と演奏者の二通りがあるように書いたが、実は、時には演奏者、時には観客というからみがある。また、さらに、今回のシュガ―オーケストラのように、中学生のオーケストラ・ワークショップ参加のようなかかわり方がある。また、新人演奏会で活躍した人が出演者になるという例も多い。さらにまた、「玉露の妖精」のように、南城市民が、オーディションで演奏者になるという流れもある。
こうした流れに、音楽芸能及びそれに関わる多様な文化ジャンルがからんでくるのだが、それらは、音楽を軸にした文化的表現にかかわるものに限定されない。演奏者・観客の精神性・日常生活を豊かにする点にも注目したい。それには娯楽あるいは癒しといったことを含むかもしれない。
そして、日常生活から離陸して高い芸術的なものを感じる場である一方で、日常生活感覚で音楽文化を楽しむという面も結構多い。民謡やジャズのように、生活のなかで楽しむ音楽も結構あるだろうし、高度な芸術的なものと日常的なものとの中間といった感じのものも多い。
シュガ―ホールの特徴は、高度に芸術的なものと見なされがちなものを、観客の感覚にフィットするように、展開する所にもある。今回のシュガ―オーケストラや組踊の公演はそうした色彩が濃厚だ。また、学校や公民館などへの各種の出前企画が、多様な展開をつなぐ橋わたし機能を果たしている点にも注目しておきたい。
(内側サイクルについて、次回に続く)
 写真は、シュガ―ホール
写真は、シュガ―ホール