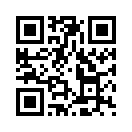2013年03月10日
「沖縄感性・文化産業シンポジウム」を聴く
8日夜、県立博物館・美術館講堂で開かれた、沖縄総合事務局主催のものだ。
私の知らない世界が一杯だった。知っている人というと、パネリストの下山久さんと平田大一さんだけで、たくさんいた聴衆のなかには、たった一人しか知人はいなかった。その知人から「浅野さんがいるなんて」といわれてしまった。
聴く話も、「文化の産業化」「エンターテイメントビジネスの振興」がテーマなのだから、「初対面」のことが大量だ。でてくる単語、とくにタレントやエンターテイナーについては、まれに知っている人がでてくるくらいだ。それに、みなさん、ひどく早口だ。まるで別世界だ。
それでも、参加動機はある。地域おこし、とくに沖縄おこし・南城おこしという事と、音楽芸能を中心とする文化、さらに歴史遺産文化遺産とを結びつけて考えることを、この一カ月足らずしてきたので、その流れで、偶然手にしたチラシを見て、出かけた。
だから、私とは関係ない、異論をもつことも多いが、勉強になり刺激を受けたことも多い。いくつか並べよう。
1)ここわずか10年ほどでの激動 CDの売上激減からライブ化へが象徴
2)キーワードが参加と変化。私自身も、80年代に指摘したことだが、静かに鑑賞するという時代から、観衆自らが参加してパフォーマンスするという事が、業界のなかでも主流になっている。
3)130万余りという沖縄の人口では、産業化できる量ではないが、600万という観光客数を入れると、日本の人口の何%かになり、産業化の検討対象になる。海外からの観光客が音楽芸能を求めてくる可能性。ハワイ、バリ、ベトナムなどの事例を参照。沖縄から海外にも音楽芸能をもって出かける。
沖縄の特徴と課題にかかわって、
1)沖縄の伝統としての強みがある文化とエンタ-テインメントとをどう関係させるのか、という問題が一つの焦点。
2)沖縄文化と観光とをどう関係づけるか。観光客は、沖縄の海洋レジャーを楽しみにくる比率が高い。沖縄の音楽や文化を楽しみたいという観光客も多いが、そうしたものを楽しめる場がとても少ない。
3)沖縄芸能は、レッスンを受けるということが中心の「習う」スタイル。それを「見せる」「発信する」というものへと発展させること。
4)文化を産業化するということは、それで生活できる職業にするということでもある。アーティストは多いが、それだけでは「食べていけない」現状。
5)アーティストは多いが、それを支えるスタッフ、マネージングする人が少なすぎる。
6)「皆がステージに立つ」と言うだけでなく、「一流」のものを育てる必要がある。
さらに、こうした問題を、文化芸能と教育とを比較して考えるとどうなるのか、とまたまた考えてしまった。いろいろと考えていきたいことが多い。
 写真は本文に関係なく、我が家ベランダから見る海岸
写真は本文に関係なく、我が家ベランダから見る海岸
私の知らない世界が一杯だった。知っている人というと、パネリストの下山久さんと平田大一さんだけで、たくさんいた聴衆のなかには、たった一人しか知人はいなかった。その知人から「浅野さんがいるなんて」といわれてしまった。
聴く話も、「文化の産業化」「エンターテイメントビジネスの振興」がテーマなのだから、「初対面」のことが大量だ。でてくる単語、とくにタレントやエンターテイナーについては、まれに知っている人がでてくるくらいだ。それに、みなさん、ひどく早口だ。まるで別世界だ。
それでも、参加動機はある。地域おこし、とくに沖縄おこし・南城おこしという事と、音楽芸能を中心とする文化、さらに歴史遺産文化遺産とを結びつけて考えることを、この一カ月足らずしてきたので、その流れで、偶然手にしたチラシを見て、出かけた。
だから、私とは関係ない、異論をもつことも多いが、勉強になり刺激を受けたことも多い。いくつか並べよう。
1)ここわずか10年ほどでの激動 CDの売上激減からライブ化へが象徴
2)キーワードが参加と変化。私自身も、80年代に指摘したことだが、静かに鑑賞するという時代から、観衆自らが参加してパフォーマンスするという事が、業界のなかでも主流になっている。
3)130万余りという沖縄の人口では、産業化できる量ではないが、600万という観光客数を入れると、日本の人口の何%かになり、産業化の検討対象になる。海外からの観光客が音楽芸能を求めてくる可能性。ハワイ、バリ、ベトナムなどの事例を参照。沖縄から海外にも音楽芸能をもって出かける。
沖縄の特徴と課題にかかわって、
1)沖縄の伝統としての強みがある文化とエンタ-テインメントとをどう関係させるのか、という問題が一つの焦点。
2)沖縄文化と観光とをどう関係づけるか。観光客は、沖縄の海洋レジャーを楽しみにくる比率が高い。沖縄の音楽や文化を楽しみたいという観光客も多いが、そうしたものを楽しめる場がとても少ない。
3)沖縄芸能は、レッスンを受けるということが中心の「習う」スタイル。それを「見せる」「発信する」というものへと発展させること。
4)文化を産業化するということは、それで生活できる職業にするということでもある。アーティストは多いが、それだけでは「食べていけない」現状。
5)アーティストは多いが、それを支えるスタッフ、マネージングする人が少なすぎる。
6)「皆がステージに立つ」と言うだけでなく、「一流」のものを育てる必要がある。
さらに、こうした問題を、文化芸能と教育とを比較して考えるとどうなるのか、とまたまた考えてしまった。いろいろと考えていきたいことが多い。
 写真は本文に関係なく、我が家ベランダから見る海岸
写真は本文に関係なく、我が家ベランダから見る海岸