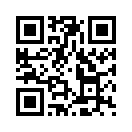2013年03月05日
音楽・シュガーホールに焦点化した南城の文化発展への提案 シュガーホールと南城おこし5
連載最終回になった。これまで書いてきたことをもとに、提案を並べていこう。
いろいろなアイデアが浮かぶ段階で、それらがまだ十分には整理深化されてはいないので、順不同で並べることになる。これまでのシュガ―ホールで展開してきた活動・企画の継続を前提とするのはいうまでもない。
1.南城市としての、町づくりと結合した文化政策づくり。その重要な軸の一つとして音楽・シュガ―ホールが位置づく。
一般的に言って他の分野と比べると政治的性格が低く見なされ、また、直接的な費用対効果が低く評価されがちな音楽・文化では、行政的サポート予算的サポートが後回しになりがちである。対照的に、南城市では、シュガ―ホールおよびその音楽活動に対して、町づくり的視点を含みつつ、職員配置予算措置を含めて強力な対応がなされてきた。それは市町村合併以前から続く歴史的伝統であり、それを継承し、さらに発展させることが求められる。
2.推進主体の形成
まず何よりも、シュガ―ホールオーケストラメンバーなどの演奏家、合唱団メンバー、そして、芸術アドバイザー、指揮者などの音楽専門家音楽者の確保拡大水準向上。
3.南城市の音楽を含む文化政策を立案するだけでなく、その実現に向けて活動する働き手集団を形成発展させる。それは、音楽専門家、市職員、市内外のボランタリーな「文化を愛し、意気に燃える」人々などで構成される。
4.3をさらに広げて、「音楽&町おこし」有志の確保と諸取り組みへの彼らの積極的関与の推進
音楽面と町おこしの両面での持続的な働き手を一定量以上組織することが不可欠である。それにふさわしい組織体制をこれまで以上に創出拡大維持していくことが必要となる。シュガ―ホール友の会メンバーがその重要な一角を占めるだろう。シュガ―ホール企画アイデア提案や実施をボランティア的に担うメンバーを、市内各地に何らかの形で組織して育てたい。
※ シュガ―ホール運営審議会が発展的改組することも視野に入れてもいいだろう。
5.多様な研究会
a.シュガーホールをめぐる研究会。あるいは、全国研究会をシュガーホールがかかわって開催
b.音楽創造に関わるワークショップ・研究会
c.町づくりと音楽・シュガ―ホールの研究会
シュガ―ホール創設以来の歴史は、たんなる「はこもの」提供ではなく、シュガ―ホールを主要場所とする音楽創造活動の展開と並行していた。それは『並みのもの』ではなく、日本全体のなかでも瞠目される取り組みの連続的展開であった。そうした歴史的伝統を継続していくことが求められる。
6.シュガーホール・アネックス「あちこち(あちこーこー)のシュガ―ホール」の設置。大里市役所・大型スーパー、学校音楽室、児童館など
出前コンサートの継続発展 お手軽音楽会、音楽カフェなどがあちこちの「シュガ―ホール」で開かれてよいだろう。
7.広報活動の活性化
a.シュガ―ホールミニコミ紙の発行
b.FMなんじょうにシュガ―ホール・コーナーを作る
c..「広報なんじょう」にシュガ―ホールコーナーをつくる
8.協同の拡大深化
これまでのシュガ―ホールの取り組み企画は、多様な協同のなかで展開されてきたが、それをさらに新たな協同の拡大深化へと進めること。
地域の音楽芸能との協同
地域の諸文化との協同 とくに、美術工芸分野との協同 文化協会との協同
町づくりのなかで
小規模の地域単位での音楽ともかかわる町づくりの動向を育てる。
地域の諸産業が音楽・文化と響き合って発展するような戦略を作り上げ展開する。
観光客を含む市外からの来訪者と共に、より豊かな音楽・文化を構築できるような体制を、住民・産業関係者・行政とともに構築していくこと。
9.諸組織・諸分野との協同
a.福祉との連携 学童保育・保育園などとも
b.学校教育との連携
c.地域産業との提携
レコーディングの場としてシュガ―ホールを生かす提案も耳にする
フリーマーケット 音楽関連品があってもよいだろう
いつかは音楽通りが誕生することを夢見るのもいいだろう
いつかは、シュガ―ホール公演鑑賞ツアーで観光客がくるようになるのもいいだろう。
d.青年会・老人会・女性会などとも提携 カラオケ大会 青年芸能祭典
10.こういった様々な取り組みの集約点として、次のようなイベント構想の企画
a.尚巴志総合文化祭典、南城市音楽祭り
欧米に著しいが、アジアでも日本でも、自然遺産歴史的遺産を現代文化創造のなかに位置づけて、町おこしをする事例があるが、南城に豊かにある自然遺産歴史遺産とかかわる音楽企画が登場させることも視野に入れたい。
b.新人演奏会と並んで、南城音楽(大)賞の創設
11.シュガ―ホール音楽塾・音楽学校の開催
12.企画の公募 1企画20~50万円予算での募集
13.2013年度からの5ケ年を、多様なことへのチャレンジとして捉える
 写真は本文に関係なく、洋蘭博覧会で撮影したもの
写真は本文に関係なく、洋蘭博覧会で撮影したもの
いろいろなアイデアが浮かぶ段階で、それらがまだ十分には整理深化されてはいないので、順不同で並べることになる。これまでのシュガ―ホールで展開してきた活動・企画の継続を前提とするのはいうまでもない。
1.南城市としての、町づくりと結合した文化政策づくり。その重要な軸の一つとして音楽・シュガ―ホールが位置づく。
一般的に言って他の分野と比べると政治的性格が低く見なされ、また、直接的な費用対効果が低く評価されがちな音楽・文化では、行政的サポート予算的サポートが後回しになりがちである。対照的に、南城市では、シュガ―ホールおよびその音楽活動に対して、町づくり的視点を含みつつ、職員配置予算措置を含めて強力な対応がなされてきた。それは市町村合併以前から続く歴史的伝統であり、それを継承し、さらに発展させることが求められる。
2.推進主体の形成
まず何よりも、シュガ―ホールオーケストラメンバーなどの演奏家、合唱団メンバー、そして、芸術アドバイザー、指揮者などの音楽専門家音楽者の確保拡大水準向上。
3.南城市の音楽を含む文化政策を立案するだけでなく、その実現に向けて活動する働き手集団を形成発展させる。それは、音楽専門家、市職員、市内外のボランタリーな「文化を愛し、意気に燃える」人々などで構成される。
4.3をさらに広げて、「音楽&町おこし」有志の確保と諸取り組みへの彼らの積極的関与の推進
音楽面と町おこしの両面での持続的な働き手を一定量以上組織することが不可欠である。それにふさわしい組織体制をこれまで以上に創出拡大維持していくことが必要となる。シュガ―ホール友の会メンバーがその重要な一角を占めるだろう。シュガ―ホール企画アイデア提案や実施をボランティア的に担うメンバーを、市内各地に何らかの形で組織して育てたい。
※ シュガ―ホール運営審議会が発展的改組することも視野に入れてもいいだろう。
5.多様な研究会
a.シュガーホールをめぐる研究会。あるいは、全国研究会をシュガーホールがかかわって開催
b.音楽創造に関わるワークショップ・研究会
c.町づくりと音楽・シュガ―ホールの研究会
シュガ―ホール創設以来の歴史は、たんなる「はこもの」提供ではなく、シュガ―ホールを主要場所とする音楽創造活動の展開と並行していた。それは『並みのもの』ではなく、日本全体のなかでも瞠目される取り組みの連続的展開であった。そうした歴史的伝統を継続していくことが求められる。
6.シュガーホール・アネックス「あちこち(あちこーこー)のシュガ―ホール」の設置。大里市役所・大型スーパー、学校音楽室、児童館など
出前コンサートの継続発展 お手軽音楽会、音楽カフェなどがあちこちの「シュガ―ホール」で開かれてよいだろう。
7.広報活動の活性化
a.シュガ―ホールミニコミ紙の発行
b.FMなんじょうにシュガ―ホール・コーナーを作る
c..「広報なんじょう」にシュガ―ホールコーナーをつくる
8.協同の拡大深化
これまでのシュガ―ホールの取り組み企画は、多様な協同のなかで展開されてきたが、それをさらに新たな協同の拡大深化へと進めること。
地域の音楽芸能との協同
地域の諸文化との協同 とくに、美術工芸分野との協同 文化協会との協同
町づくりのなかで
小規模の地域単位での音楽ともかかわる町づくりの動向を育てる。
地域の諸産業が音楽・文化と響き合って発展するような戦略を作り上げ展開する。
観光客を含む市外からの来訪者と共に、より豊かな音楽・文化を構築できるような体制を、住民・産業関係者・行政とともに構築していくこと。
9.諸組織・諸分野との協同
a.福祉との連携 学童保育・保育園などとも
b.学校教育との連携
c.地域産業との提携
レコーディングの場としてシュガ―ホールを生かす提案も耳にする
フリーマーケット 音楽関連品があってもよいだろう
いつかは音楽通りが誕生することを夢見るのもいいだろう
いつかは、シュガ―ホール公演鑑賞ツアーで観光客がくるようになるのもいいだろう。
d.青年会・老人会・女性会などとも提携 カラオケ大会 青年芸能祭典
10.こういった様々な取り組みの集約点として、次のようなイベント構想の企画
a.尚巴志総合文化祭典、南城市音楽祭り
欧米に著しいが、アジアでも日本でも、自然遺産歴史的遺産を現代文化創造のなかに位置づけて、町おこしをする事例があるが、南城に豊かにある自然遺産歴史遺産とかかわる音楽企画が登場させることも視野に入れたい。
b.新人演奏会と並んで、南城音楽(大)賞の創設
11.シュガ―ホール音楽塾・音楽学校の開催
12.企画の公募 1企画20~50万円予算での募集
13.2013年度からの5ケ年を、多様なことへのチャレンジとして捉える
 写真は本文に関係なく、洋蘭博覧会で撮影したもの
写真は本文に関係なく、洋蘭博覧会で撮影したもの